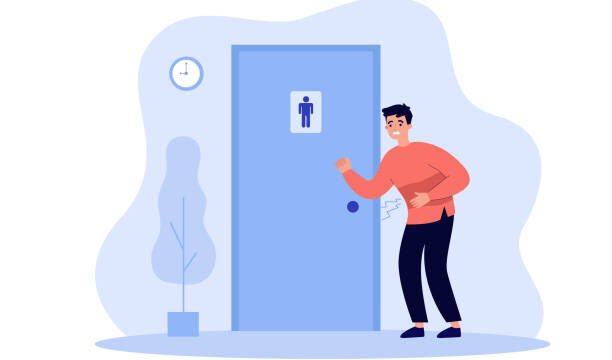*診断書の発行は医師の専門的な判断に基づくものであり、場合によっては当日発行できないことがあります。最終的な診断書の発行は医師の裁量に委ねられていますので、ご了承ください。
「過敏性腸症候群で仕事を休職する流れは?」
「治療法や休職中の過ごし方のポイントが知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
過敏性腸症候群の症状が重く、仕事に支障をきたす場合は休職を検討することも大切です。
本記事では、過敏性腸症候群で仕事を休職する流れや治療法について詳しく解説します。過敏性腸症候群でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
なお、過敏性腸症候群でお悩みの方は、横浜心療内科・精神科よりそいメンタルクリニックにご相談ください。患者様の症状を見極めて適切な治療を提供いたします。
過敏性腸症候群がつらい場合は休職できる?

過敏性腸症候群(IBS)は、日常生活に大きな影響を与える可能性があります。症状が重く、仕事に集中できない場合は、休職を検討することも選択肢の一つです。
会社によっては、体調不良を理由に休職を許可する制度がありますので、職場の人事担当者や直属の上司に相談してみることが重要です。
休職の際は病院の診断書は必要?
過敏性腸症候群で休職する場合、診断書が必要となるケースが多くあります。会社の休職規定によっては医師の証明が求められることがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
診断書は、主治医に相談して発行してもらうことができます。診断書には、疾病名や症状、休職期間の目安などが記載されることが一般的です。
また、診断書を提出することにより、休職に伴う誤解やトラブルを避けることができますので、しっかりと準備しておくことが望ましいでしょう。
上司や人事からの信頼を得る一助にもなるため、診断書の提出は行いましょう。
病院で診断書を受け取るメリット

診断書を病院で受け取ることには様々なメリットがあります。
- スムーズに休職が進む
- 業務量などを配慮してもらえる
- 各種公的福祉制度を活用できる
それぞれのメリットを確認していきましょう。
スムーズに休職が進む
診断書を取得することで、休職申請がスムーズに進みます。
職場によっては、単なる口頭での申し出では休職が認められにくい場合がありますが、診断書があれば「医師の勧め」として正式に扱われるため、迅速に休職手続きが完了する可能性が高まります。
また、診断書があることで職場からの理解も深まりやすく、理由の確認などの手続きが省略され、余計なストレスを抱えることなく休養に入ることができるのです。
業務量などを配慮してもらえる
診断書が職場に提出されることで、上司や同僚からの業務の配慮を受けやすくなります。
例えば、診断書には医師による体調面での具体的な制限や注意点が記載されている場合もあります。
それに基づいて、体調の変化にも正確に対応し、必要に応じて業務の軽減や調整をしてもらえる可能性があります。
このように、診断書は働く上でのサポート体制を受けるための鍵となります。
各種公的福祉制度を活用できる
診断書は公的福祉制度の利用時に欠かせない書類のひとつです。例えば、健康保険からの給付金の申請や傷病手当金制度の申請などにも診断書が必要となります。
公的福祉制度に申請することで経済的負担が減少し、治療に専念できる環境が整います。また、診断書は介護や障害に関する支援制度の利用においても必要となるため、早期に取得し、適切に活用することが重要です。
診断書を取得することで、様々な福祉制度を利用でき経済的な負担を軽減できます。
過敏性腸症候群で休職する流れ

過敏性腸症候群は症状が深刻化すると、日常生活や職場での業務に支障をきたす可能性があります。そのため、早期の適切な治療と休養が求められます。
過敏性腸症候群で休職を検討する際の流れを7つのステップで紹介します。
- 【ステップ1】心療内科や消化器内科を受診する
- 【ステップ2】医師の診察、診断を受ける
- 【ステップ3】診断を受けたら発行依頼をする
- 【ステップ4】治療方針を決定する
- 【ステップ5】会社に診断書を提出して休職を願い出る
- 【ステップ6】業務の引き継ぎを行う
- 【ステップ7】休職して療養に入る
それぞれ確認していてスムーズに治療を受けられるようになりましょえ。
【ステップ1】心療内科や消化器内科を受診する
まずは心療内科や消化器内科を受診しましょう。症状が出てたら一人で抱え込まず、専門医に相談することが重要です。
医師は症状の原因や程度を適切に診断し、最適な治療プランを提案してくれます。初回受診時には、自分の症状や発生状況を詳細に伝えるように心掛けましょう。
こうした情報が、正確な診断につながります。
【ステップ2】医師の診察、診断を受ける
診察や検査を経て、医師は過敏性腸症候群かどうかを確認します。診断が確定した場合、症状の度合いや本人の状態に応じた治療法が提示されます。
医師の説明をしっかりと理解し、必要であれば疑問点を解消することが大切です。
治療方法の選択や職場環境の調整などについても相談してみましょう。
【ステップ3】診断を受けたら発行依頼をする
診断が確定したら、必要に応じて診断書の発行を医師に依頼します。
休職のために診断書が必要である旨をしっかりと伝えておくことが重要です。診断書には、症状の詳細や治療方針、休職の期間が記載されます。
職場へ提出するため、情報が適切に記載されていることを確認しましょう。
【ステップ4】治療方針を決定する
医師と相談の上、具体的な治療方針を決定します。過敏性腸症候群の治療には、薬物療法、カウンセリング、食事療法などがあります。
個々の症状や生活習慣に合わせて、最適な治療方針を決定します。
また、必要に応じて生活環境の改善やストレス対策も取り入れましょう。
【ステップ5】会社に診断書を提出して休職を願い出る
医師から発行された診断書を元に、上司や人事担当者に休職を願い出ます。診断書は、休職が必要とされる理由を理解してもらうために重要な役割を果たします。
会社側とコミュニケーションを取りながら、具体的な休職期間や業務の調整について話し合いましょう。
理解してもらうことで、よりスムーズに療養することが可能です。
【ステップ6】業務の引き継ぎを行う
休職が決まったら、担当している業務の引き継ぎを行い、チームや同僚に負担が掛からないように配慮します。
引き継ぎは、業務の継続性を保つために重要なステップです。引き継ぎの詳細や必要な資料を準備し、可能な限り円滑に進めましょう。
会社との信頼関係を保つうえで引き継ぎはとても重要です。
【ステップ7】休職して療養に入る
正式に休職が認められたら、体調を整えることに集中しましょう。
心と体のリフレッシュを図り、医師の指導のもとで適切に療養を続けてください。
焦らず、しっかりと体調を整えてから職場復帰を目指しましょう。
診断書をすぐにもらうためのポイント

診断書がすぐに必要な場合は、診断書をすぐにもらうためのポイントを4つ紹介します。
- 過敏性腸症候群に関する具体的な症状に悩んでいることを医師に伝える
- 診断書の当日発行に対応しているクリニックに相談する
それぞれ確認していきましょう。
過敏性腸症候群に関する具体的な症状に悩んでいることを医師に伝える
過敏性腸症候群は、腹痛や腹部不快感、便秘や下痢などの症状が特徴です。これらの症状が日常生活にどのように影響を与えているか、具体的に医師に伝えることが大切です。
例えば、特定の食事を摂ると症状が悪化する、または社会的な場面で症状が現れるといった具体例を挙げると良いでしょう。
また、過去に試した治療法やその効果についても情報共有しておくと、医師が診断を下す上での手助けになります。
こうした具体的な情報は、医師が迅速かつ的確に診断を行うための重要な手がかりとなります。
診断書の当日発行に対応しているクリニックに相談する
中には、診断書の当日発行に対応しているクリニックもあります。
予約時に診断書が必要であることを事前に伝え、当日発行に対応可能かどうか確認すると良いでしょう。
診療内容や混雑状況によっては時間がかかることもあるため、可能であれば余裕を持ってクリニックを訪れることが望ましいです。
過敏性腸症候群の治療法

過敏性腸症候群は個々の症状に応じた治療が求められます。基本的な治療法としては以下のものがあります。
- 食生活の改善
- 薬物療法
- 精神療法
それぞれの治療法は、病状の改善だけでなく、患者の日常生活の質を向上させることにもつながります。それぞれ確認していきます。
食生活の改善
過敏性腸症候群の治療において、食生活の改善は重要な要素です。まず、食物繊維の摂取量を調整することが大切です。
便秘タイプの患者は、適度な食物繊維の増加が役立つことがありますが、下痢タイプの患者は過剰摂取を避けることが重要です。
また、乳製品や脂肪分の多い食品、カフェイン、アルコールなどの刺激物は症状を悪化させる可能性があるため、これらの摂取を控えることが望ましいです。
個人差があるため、特定の食材や飲料が症状に影響を与えるかどうかを見極めながら食事の調整を続けることが大切です。
薬物療法
過敏性腸症候群の症状を緩和するために、医師の指導の下での薬物療法が行われることがあります。
便秘タイプの患者には繊維剤や便軟化剤が、下痢タイプの患者には下痢止め薬が処方されることがあります。
また、腹痛を軽減するために、抗けいれん薬が使用されることもあります。症状がひどい場合や精神的なストレスが症状を悪化させている場合には、抗うつ薬や抗不安薬が処方されることもあります。
これらの薬の効果は個人差がありますので、医師と相談しながら適切な薬を選ぶことが重要です。
精神療法
過敏性腸症候群の症状は、ストレスや不安などの心理的要因によって悪化することがあります。そのため、精神療法は治療において重要な役割を果たします。
認知行動療法は、症状を管理するための考え方や行動を変える手助けをし症状の改善が期待できます。
また、マインドフルネスやヨガなどのリラクゼーション技術もストレスを軽減し、腸の健康をサポートします。
精神療法によって得られる心の安定が、結果的に腸の症状緩和に寄与することが期待されます。
過敏性腸症候群で休職中の過ごし方

過敏性腸症候群はストレスや生活の乱れなどが原因で症状が悪化することがあるため、休職中の過ごし方は非常に重要です。
休職中は自宅でリラックスしながら回復を目指し、生活習慣を見直す絶好の機会です。
日常生活において心地よい時間を過ごすためのポイントを押さえ、可能な限りストレスを軽減することが大切です。
これにより、復職後の生活にも良い影響をもたらすことができるでしょう。
十分な休息をとる
過敏性腸症候群の症状を和らげるためには、身体と心に十分な休息を与えることが欠かせません。
休職中は無理をせず、自分のペースでリラックスできる時間を確保しましょう。就寝時間を一定にしたり、昼寝を適度に取り入れることで、体力を回復させることができます。
また、リラックス効果のある音楽を聴いたり、深呼吸や瞑想を行うと心身ともにゆったりとした時間を過ごせます。十分な休息は心と体の健康回復の基礎です。
ストレスのない環境を整えて
休職期間中はできる限りストレスのない環境を整えることが重要です。
生活空間を整理整頓し、居心地の良い環境を作りましょう。自分の好きな香りを使ったアロマディフューザーを利用するのも効果的です。
また、ストレスを増やす要因となり得るインターネットやSNSの利用を控え、静かな時間を大切にすることもおすすめです。
自然の中を散歩することでリフレッシュするなど、自身がリラックスできる活動を探してみてください。
食事に気をつける
食事は過敏性腸症候群の症状に直接的な影響を与えることが多いため、慎重に選ぶことが重要です。
刺激が強く消化に負担がかかる食品(辛いもの、脂っこいもの、カフェインなど)は控え、バランスの取れた栄養価の高い食事を心がけましょう。
食物繊維が豊富な食材や発酵食品を取り入れることで、腸内環境を整える助けになります。
また、食事はゆっくりと時間をかけて食べることで、消化を助けることができるので意識してみてください。
適度な運動をする
適度な運動は心身のリフレッシュに効果的であり、過敏性腸症候群の症状の緩和が期待できます。
無理のない範囲で散歩やストレッチ、ヨガなどを日常に取り入れてみましょう。これによりストレスが軽減され、血流も良くなり、消化機能の改善にも期待できます。
特に自然の中でのウォーキングや深呼吸を含む簡単な運動は、精神的な解放感を得られるため、おすすめです。運動後の爽快感を味わうことで心地よい一日を送れます。
アルコールを控える
アルコールは腸に対して刺激となり、過敏性腸症候群の症状を悪化させることがあるため、摂取を控えることが望ましいです。
特に休職中の回復期間においては、できる限りアルコールの摂取を減らし、その間に不安感や緊張感を緩和する別の方法を探してみましょう。
アルコールの代わりにハーブティーを楽しむなど、心を落ち着ける飲み物を取り入れるのも良いアイデアです。
固有のリラックス方法を見つけることで、心身ともに健やかな生活を目指しましょう。
規則正しい生活を送る
規則正しい生活は、体内リズムを整える上で非常に重要です。過敏性腸症候群の症状を改善するためには、毎日の生活習慣を一定に保つことが大切です。
起床時間・就寝時間・食事時間を一定にすることで、体内時計を整え、胃腸への負担を軽減します。
また、朝日を浴びることで体内リズムがリセットされるため、朝の散歩を習慣にすると良いでしょう。こうした生活習慣の見直しが、回復の大きな一歩となるでしょう。
過敏性腸症候群で休職中に利用可能な制度

休職中に仕事を続けられない期間に給与や医療費の心配を軽減するための公的支援は多々あります。
- 傷病手当金制度
- 自立支援医療制度
それぞれの制度を理解して休職中に申請してみましょう。
傷病手当金制度
この制度は、健康保険に加入している方が病気やケガで仕事ができない場合に、給与の一部を補償するものです。
過敏性腸症候群で勤務が難しい状況でも、連続して4日以上休職した場合から手当が支給されます。
支給額は給与の約2/3であり、最長で1年6カ月間受け取ることができます。この制度を活用することで、休職中の経済的な不安を軽減し、治療に専念する環境が整います。
申請方法や必要な書類については、所属する健康保険組合の指示に従うことが重要です。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、特定の疾患に対する医療費を助成する仕組みで、過敏性腸症候群のように継続的な治療が必要な場合に役立ちます。
この制度により、自己負担額が軽減され、長期にわたる治療が経済的に負担になりにくくなります。
申請には、主治医からの診断書や必要書類の提出が求められますが、一度認定されれば精神科や心理療法、消化器内科での治療費助成を受けることができます。
過敏性腸症候群での休職に関するよくある質問

最後に、過敏性腸症候群での休職に関するよくある質問を3つ紹介します。
- 診断書がなくても休職はできますか?
- どれくらいの期間休職できますか?
- 診断書の発行費用はどれくらいですか?
それぞれ確認して、疑問や悩みの解消に役立ててください。
診断書がなくても休職はできますか?
基本的に、正式な休職手続きを行うためには診断書が必要です。診断書は、医師があなたの健康状態を確認し、業務に支障をきたすと判断した際に発行されます。
しかし、職場によっては事情を説明すれば休職を取ることができる場合もあります。
制度や手続きは職場によって異なるため、直属の上司や人事部に相談してみると良いでしょう。
どれくらいの期間休職できますか?
休職期間は、病状や職場の規定によって異なります。通常、医師の診断書に基づき、必要な期間が設定されます。
初めは数週間程度の短い休職から始め、その後の経過観察により延長することも可能です。
また、会社の休職制度や有給休暇を利用して、その都度対処することもあります。会社の就業規則や医師のアドバイスに沿って無理なく療養することが大切です。
診断書の発行費用はどれくらいですか?
診断書の発行には費用がかかることが一般的です。通常は数千円から一万円程度の範囲ですが、病院やクリニック、そして地域によっても費用は異なります。
発行にかかる時間や予約の有無も事前に確認しておくことをおすすめします。また、健康保険は適用されないことが多いので、その点も考慮しておきましょう。
費用について心配がある場合は、受診前に電話で確認してきましょう。
過敏性腸症候群を疑ったら早めにクリニックに相談を!

過敏性腸症候群の兆候を感じたら、早めに専門の医師に相談することが重要です。症状が軽度のうちに診断を受け、適切な治療を開始することで、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
早期診断により、症状の悪化を防ぐだけでなく、適切な治療法を見つけやすくなるでしょう。自身の健康管理のためにも、医療機関への相談をためらわず行いましょう。
過敏性腸症候群でお悩みの方は、横浜心療内科・精神科よりそいメンタルクリニックにご相談ください。患者様の症状を見極めて適切な治療を提供いたします。