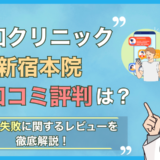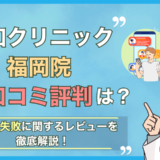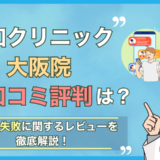*診断書の発行は医師の専門的な判断に基づくものであり、場合によっては当日発行できないことがあります。最終的な診断書の発行は医師の裁量に委ねられていますので、ご了承ください。
「パワハラやモラハラで診断書はもらえる?」
「休職の流れや注意点が知りたい」
このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
パワハラやモラハラは心理面に大きな負担となるため注意が必要です。
本記事ではパワハラやモラハラでの診断書のもらい方や休職の流れを紹介します。
なお、パワハラやモラハラでお悩みの方は、よりそいメンタルクリニックにご相談ください。患者様の症状を見極めて適切な治療を提供いたします。
職場のパワハラやモラハラで休職は可能!

職場でのパワハラやモラハラは、働く人々を深刻なストレスにさらす問題です。
こうした行為により心身の健康が損なわれた場合、一時的な休職を検討することも大切となります。
医療機関からの診断書があれば、休職が認められることがほとんどです。
そのため、パワハラやモラハラで休職を検討する際はクリニックに相談して診断書の発行を依頼しましょう。
パワハラとは?
パワハラとは、権限や立場を利用して、相手に精神的、身体的な苦痛を与える行為のことを指します。
具体的には、怒鳴りつける、過剰な業務を課す、意見を無視するなどが挙げられます。
被害を受けた側は自己評価の低下や仕事に対する意欲の喪失だけでなく、身体的な不調を訴えることも少なくありません。
パワハラは組織全体の士気を下げ、生産性を低下させる危険性があるため、早期の発見と解決が重要です。
モラハラとは?
モラハラとは、精神的な領域で他者を攻撃し、屈辱や恐怖心を与える行動を指します。
これは言葉や態度を用いた精神的な圧力や支配を特徴とし、時には相手を孤立させたり、侮辱したりします。
モラハラの背後には、加害者の優位性を誇示したいという心理があることが多いです。
モラハラは長期間にわたり持続することが多く、被害者の精神的な健康を著しく損なう可能性があるため早期に専門家に相談することが推奨されます。
パワハラやモラハラで発症する精神疾患

パワハラやモラハラといった精神的なストレスは、さまざまな精神疾患を引き起こす要因となります。
- うつ病
- 双極性障害
- 適応障害
- 不安障害
- 自律神経失調症
- 睡眠障害
- 統合失調症
以下に、特に注意が必要な精神疾患について詳しく解説します。確認していきましょう。
うつ病
うつ病は、パワハラやモラハラの被害者に最も一般的に見られる精神疾患の一つです。
これらのハラスメントは、自己評価の低下や無力感、絶望感を引き起こすことがあり、それが長期的に続くと、感情の落ち込みや無気力といったうつ病の症状を現すようになります。
早期の対応や治療が重要であり、専門の医療機関での受診やカウンセリングが推奨されます。
双極性障害
双極性障害は、気分の波が激しく、躁状態とうつ状態が交互に現れるのが特徴です。
パワハラやモラハラは、こうした気分の不安定性を助長することがあります。
特に職場や家庭での精神的な圧力が強い環境では、感情の制御が難しくなり症状が悪化する可能性があります。
医師の監督の下での治療が必要で、自己管理やサポート体制の整備も重要です。
適応障害
適応障害は、特定のストレス源に対して過度に強い反応を示し、日常生活に支障が出る疾患です。
パワハラやモラハラは、強いストレス源となり得ます。
適応障害の症状には、憂鬱感や不安、引きこもりなどがあります。
ストレスへの耐性を高めるためのカウンセリングや、ストレス管理の技術を学ぶことが有効です。環境の改善も症状の軽減につながります。
不安障害
不安障害は、強い不安感や恐怖感が持続し、日常生活に悪影響を及ぼす状態です。
パワハラやモラハラによる心の負担は、不安障害の発症を促す可能性があります。
常に何かに怯える感覚や予期不安がつきまとい、集中力を欠くことが多くなります。
自律神経失調症
自律神経失調症は、体のさまざまな部位に症状が現れる疾患で、ストレスが主な原因となります。
パワハラやモラハラによって過度なストレスがかかると、自律神経のバランスが崩れ、頭痛やめまい、動悸や不眠といった症状が引き起こされます。
症状の改善には生活習慣の見直しやリラクゼーションが効果的です。ストレスを減らすための対策として心理的支援を受けることも対応です。
睡眠障害
睡眠障害は、眠りの質や量に問題が生じる疾患です。パワハラやモラハラによる精神的ストレスが、寝つきの悪さや中途覚醒といった形で表れます。
不眠が続くと、日中の集中力や記憶力が低下し、生活の質が悪化します。
ストレス管理と共に、規則正しい生活やリラックス法の実践が求められます。医療機関でのアドバイスも有効です。
統合失調症
統合失調症は、現実との接触が妨げられ、幻覚や妄想が主な症状として現れる重篤な疾患です。
パワハラやモラハラは、特に感受性の高い人において、その発症を誘発する一因となることがあります。
早期診断と治療が極めて重要であり、適切な薬物療法と心理療法の併用が必要です。
社会的なサポートと環境の調整も回復を支援する大きな要素となります。
パワハラやモラハラでの診断書のもらい方

職場でのパワハラやモラハラは、精神的な健康に大きな影響を与えることがあります。被害を受けた際には、自分を守るために診断書を取得することが重要です。
以下では、診断書の入手までの具体的な手順をご紹介します。
- 心療内科・精神科クリニックに予約をとる
- 医師の診察・診断を受ける
- 診断書の発行を依頼する
- 診断書を受け取る
それぞれ確認してスムーズに診断書を受け取れるようになりましょう。
心療内科・精神科クリニックに予約をとる
まずは、心療内科や精神科クリニックに連絡して予約を取りましょう。
クリニックは検索サイトや口コミを利用して、自分に合った場所を探すようにしてください。
初めて訪れる場合は予約時にパワハラやモラハラに関する相談を希望していることを伝えておくとスムーズです。
混雑しているクリニックでは予約が取りにくいこともあるので、早めに予約を取ることをおすすめします。
医師の診察・診断を受ける
予約した日程にクリニックを訪れ、医師の診察を受けます。
その際には、職場での具体的な状況や自身の感じている症状を正直に伝えましょう。
医師はそれに基づいて、心の状態やストレスのレベルを評価し必要な診断をしてくれます。
診断を受けることで、パワハラやモラハラによる影響を客観的に理解することができます。
診断書の発行を依頼する
診断が終了し、医師が診断書が必要と判断した場合には、診断書の発行を依頼します。
診断書には、診断名や診断日、症状の程度、治療の必要性などが記載されます。
事前に発行にかかる費用や日時を確認しておくと良いでしょう。
診断書を受け取る
診断書が発行されたら、クリニックから手渡されます。場合によっては郵送してもらえることもありますが、受取方法は予め確認しておくと安心です。
診断書を受け取ったら、その内容を確認し、必要に応じて職場や弁護士に提出します。
診断書は重要な文書なので厳重に保管しましょう。
また、診断書を受け取る際は内容を確認しておき記入内容に誤りがないか確認しておきましょう。
診断書をすぐにもらうためのポイント

クリニックで診断書をすぐにもらうためのポイントを紹介します。
- 自身の症状が精神疾患に当てはまるか基準を確認しておく
- 診断書の当日発行に対応しているクリニックに相談する
それぞれ確認して早めに診断書をもらえるようにしましょう。
自身の症状が精神疾患に当てはまるか基準を確認しておく
診断書をすぐに取得するためには、まず自身の症状がどのような精神疾患に分類されるのか、一般的な基準を把握しておくことが重要です。
精神疾患には多岐にわたる種類がありますが、それぞれに診断基準が存在します。
DSM-5やICD-10といった国際的な診断基準を参照し、自分の症状がどれに該当するかをあらかじめ調べておくと、医師とのコミュニケーションがスムーズになり、診断も迅速に進む可能性が高まります。
また、ご自身の症状や過去の病歴についても正確に伝えられるよう、メモを用意して医師との面談に臨むと良いでしょう。
診断書の当日発行に対応しているクリニックに相談する
診断書が必要であり、特に緊急を要する場合、当日発行に対応しているクリニックを選ぶことが必要です。
まず、インターネットや電話で、各クリニックが提供しているサービスを調べ、即日対応が可能かどうかを確認することが大事です。
受付時間や診察を行っている時間帯も合わせて確認し、混み具合や予約状況を考慮して早めに訪れることをおすすめします。
特に初診の場合は、症状の説明に時間を要する場合があるため、余裕を持って行動することも大切です。
診断書を受け取る際の注意点

診断書を受け取る際には、事前に確認すべき点がいくつかあります。
- 診断書の発行には費用がかかる
- 診断書の発行スピードはクリニックによって異なる
- 診断書は保険適応外
それぞれの注意点を理解した上で発行の依頼をしてください。それぞれ確認していきます。
診断書の発行には費用がかかる
診断書を発行してもらう際には、一般的に別途費用がかかります。
この費用は医療機関によって異なることが多く、数千円から数万円程度の差があるかもしれません。
診断書の内容や用途によって料金が変わることもあるため、事前に医療機関に確認するようにしましょう。
また、費用の支払い方法についても、現金のみの対応である場合やカード決済が可能な場合など様々ありますので、受け取り時に混乱が生じないように事前準備が必要です。
診断書の発行スピードはクリニックによって異なる
診断書の発行スピードは、クリニックや病院によって大きく異なることがあります。
急ぎの診断書が必要な場合は、あらかじめ発行がスピーディーであるか確認すると良いでしょう。
一般的には、即日発行は難しいことが多いため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
診断書は保険適応外
診断書の作成には健康保険が適用されないため、全額を自己負担する必要があります。
医療費の一部として保険が適用されることを期待される方もいるかもしれませんが、制度上診断書の発行はあくまで個別の書類作成として扱われるため、通常はこのように保険は利用できません。
ですので、診断書発行にかかる費用を予め準備することが重要です。
特に、複数の診断書や詳細が必要な場合には、思わぬ高額となる可能性もあるため、注意が必要です。
パワハラやモラハラで休職するためには?

職場でのパワハラやモラハラは深刻な問題であり、精神的にも肉体的にも大きな影響を及ぼすことがあります。
こうした状況においては、適切な対応策を講じることが重要です。
休職を考える際には、まず心身の健康を最優先に考えるべきですが、そのためにはいくつかのステップを踏む必要があります。
- 【ステップ1】診断書を会社に提出して休職を願い出る
- 【ステップ2】可能であればパワハラやモラハラが原因であることを伝える
- 【ステップ3】業務の引き継ぎを行う
- 【ステップ4】休職して療養に入る
特に診断書の提出や原因の提示など、具体的な手続きを理解することが、スムーズな休職につながります。それぞれの流れを確認していきましょう。
【ステップ1】診断書を会社に提出して休職を願い出る
信頼できる医師を受診し、自分の心身の状態を確認することが必要です。
診断書を医師から受け取ったら、それを会社に提出し、正式に休職を願い出ます。診断書は休職のための根拠となり、職場が休職を認める上で重要な役割を果たします。
診断書には、可能であれば休職期間の目安や、どのような治療が必要かを記載してもらうと良いでしょう。
診断書の内容によって、職場での対応が異なることがありますので正確に状況を医師に伝えることが大切です。
【ステップ2】可能であればパワハラやモラハラが原因であることを伝える
診断書を提出する際に、信頼できる上司や人事担当者に対して、可能であればパワハラやモラハラが休職の原因であることを伝えます。
具体的な状況を詳細に説明することが難しい場合でも、被害を受けたという事実を伝えるだけでも企業側の認識に変化を与える可能性があります。
特に、今後の改善策を講じるために企業が重要な情報を得るきっかけとなります。
ただし、伝える相手や方法については慎重に考え、自分の安全とプライバシーが守られるように配慮が必要です。
【ステップ3】業務の引き継ぎを行う
休職に入る前には、できる限り自分の業務を他の人に引き継ぐ準備を整えることが重要です。
引き継ぎの際は、自分の担当している業務の詳細や進行状況を明確に整理し、新しい担当者がスムーズに業務を続けられるようにします。
職場に迷惑をかけずに休職を開始するための配慮になるだけでなく、自分自身の心の負担も軽減することにつながります。
引き継ぎ事項は文書化しておくと後々のやりとりがスムーズです。
【ステップ4】休職して療養に入る
休職に入ったあとは療養と心身の回復に専念します。この期間は、自分自身を労わり、適切な治療を受けることに集中することが大切です。
治療プランに従い、心身のバランスを取り戻すために、必要に応じて専門家と相談しながら進めていきましょう。
社会の支援制度や、同じ悩みを抱える人々と交流することで、回復の助けになることもあります。
また、復職に関する心配事については主治医や信頼できる方に相談してアドバイスを受けることも一つの方法です。
会社に休職を伝える際のポイント

会社に休職を伝える際には、誠実に事実を説明することが大切です。また、休職の理由を適切に伝えることで、職場内での誤解や不安を最小限に抑えることができます。
会社に休職を伝える際のポイントをいくつか紹介します。
- 可能であればパワハラやモラハラが原因であることを伝える
- あらかじめ話す内容をメモしておく
- 直接会って話すのが難しい場合はメールでも可能
上司や人事部と円滑なコミュニケーションを心掛け、必要な手続きを迅速に進めるようにしましょう。それぞれ確認していきます。
可能であればパワハラやモラハラが原因であることを伝える
休職の理由がパワハラやモラハラが原因である場合は、できる限りその旨を伝えることが望ましいです。
具体的な事例や証拠がある場合はそれらを提示し、自身の精神的負担について説明することで、会社としても適切な対応を促すことができます。
ただし、伝える際には感情的にならないよう冷静に話すことが大切です。
また、これにより会社の問題改善を促すことができるので、今後の職場環境の改善にもつながります。
あらかじめ話す内容をメモしておく
休職を申し出る際は、あらかじめ話す内容をメモにまとめておくと、スムーズに話を進めることができます。
休職の理由や期間、必要なサポートについて具体的に整理しておくことで、会話が円滑になり、不安を減らせます。
メモを用意することで、重要なポイントを漏れなく上司や人事に伝えることができ、後で誤解が生じるリスクも軽減できます。
事前準備は、話し合いをより建設的なものにします。
直接会って話すのが難しい場合はメールでも可能
場合によっては、直接会って話すのが難しいことがあります。そのような場合は、メールでの連絡も選択肢に入れて考えるべきです。
メールで休職の意向を伝える際には、事情を丁寧に説明し敬意を払って書くことが重要です。
メールは証拠としても残るため、内容の正確性に注意し誤解を招かないように努めましょう。
休職中の過ごし方

休職期間は心身の回復を図る大切な時間です。働くことに疲れ、ストレスを抱えている場合、この期間を利用してリフレッシュし再びエネルギーを充電することができます。
この期間は無理をせず、自分のペースで過ごすことが重要です。さまざまな活動や趣味に没頭したり、普段後回しにしていたことをゆっくり取り組むのも良いでしょう。
休職中の過ごし方を意識することでスムーズな回復が期待できます。
十分な休息を取る
まず最初に大切なのは、しっかりと休息を取ることです。心身ともに疲弊していると、何をするにも意欲が湧きません。
日中はゆっくりと過ごし、夜は十分な睡眠を確保
するよう心がけましょう。昼寝や短い休息を取り入れることも効果が期待できます。
この期間は無理に活動しようとせず、リラックスして体を休めることを優先しましょう。
ストレスのかからない生活を送る
休職中はできるだけストレスを避け、心穏やかな生活を送りましょう。ストレスの原因となる活動や情報から距離を置き、自分が心地よく感じられる環境を整えることが大切です。
たとえば、自然に触れたり、趣味に没頭したりする時間を増やすのも良い方法です。
また、リラクゼーション法やマインドフルネスを取り入れて、心の安定を図るのも効果的です。
自分のペースで心のゆとりを大切にしながら、少しずつ前向きな気持ちを取り戻していきましょう。
規則正しい生活を意識する
休職中でも、規則正しい生活リズムを保つことを意識しましょう。生活リズムの乱れは、心身の負担となり回復を遅らせることがあります。
毎日の起床・就寝時間を一定にし、食事の時間や日常のルーチンを整えることが重要です。
自宅での過ごし方にも一定のルールを設けることで、日常生活に秩序をもたらし、精神的な安定感を保つことができます。
安定した生活習慣は、心身の健康をサポートし、次のステップへ向けての基盤を形成します。
栄養バランスの取れた食事を取る
体調を整えるためには、栄養バランスの取れた食事を心掛けることが重要です。休職期間中は、自炊を楽しむ時間を増やし、食材選びにこだわってみましょう。
栄養価の高い野菜や果物を日々の食事に取り入れ、タンパク質やビタミン、ミネラルが不足しないように意識することが大切です。
食事を通じて適切な栄養を摂取することで、体力を少しずつ取り戻し、心の調子も向上させることができます。
また、穏やかな食事を設けることで、日々のリズムが整い、充実した時間を過ごすことができます。
適度な運動を取り入れる
適度な運動は、心身の健康を維持するために非常に効果的です。休職期間中は、無理のない範囲で軽い運動を取り入れてみてください。
ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、心地よく続けられる運動を選ぶことがポイントです。
運動を日常生活の一部として取り入れることで、気分がリフレッシュされ、ストレスの軽減にもつながります。
心地よい疲労感が得られる程度の運動は、睡眠の質も向上させ、結果として心身が軽く感じられるようになるでしょう。
パワハラやモラハラから身を守るための行動

パワハラやモラハラは、働く場において深刻な問題とされています。被害を受けた場合は、一人で悩まずに以下のような適切な行動を取ることが重要です。
- 会社の上層部や相談窓口に相談する
- 社外の公的機関に相談する
- 弁護士に相談する
ここでは、具体的にどのような相談先があるのか、いくつかの手段を紹介します。
会社の上層部や相談窓口に相談する
まずは、社内の上層部やハラスメント相談窓口に相談することを検討しましょう。
特に大企業では、社員の声を真摯に受け止めるために専用の相談ルートを用意していることが一般的です。
こうしたルートは被害を受けた社員を保護し、問題の解決に向けた適切な対応を取るために設けられています。
関連する証拠や状況を整理して提出することで、問題解決のスピードも向上します。
社外の公的機関に相談する
社内での解決が難しい場合は、労働基準監督署や労働局といった社外の公的機関に相談するのも有効です。
これらの機関は、労働者の保護と職場の公正さを保つことを目的としています。
匿名での相談が可能な場合もあり、心理的な負担を軽減しながら問題解決の糸口を見つけられます。
また、法令に基づいた適切な対応を実施してもらえる点で信頼性があります。
公的機関は特定企業の内情について客観的な視点を持ち、問題の解決に向けた具体的なアドバイスをくれるでしょう。
弁護士に相談する
場合によっては、弁護士に相談することも視野に入れましょう。弁護士は法律の専門家として、パワハラやモラハラに対して法的な観点からアドバイスを提供してくれます。
特に被害が深刻な場合や、法的手段を検討してみましょう。
その結果、安心して働ける環境を作ることができます。
パワハラやモラハラが少ない仕事

パワハラやモラハラが少ない環境で働きたいという方にはいくつかの選択肢があります。
- 在宅ワーク(ライター、デザイナー)
- トラック運転手
- 清掃員
- 警備員
このような仕事では、個人の裁量が重視され、他者との直接的なコミュニケーションよりも、自分のペースで進められる作業が多いことが特徴です。それぞれ確認していきます。
在宅ワーク(ライター、デザイナー)
在宅ワークは近年ますます普及しており、ライターやデザイナーといった専門職はその代表例といえます。
これらの仕事では、自宅から自身のペースで仕事を進めることができます。
クライアントとのやり取りもメールやチャットツールを使用することが一般的で、必要最低限のコミュニケーションで進行できるため、直接的なパワハラやモラハラに遭うリスクが低く抑えられます。
また、フリーランスとして活動する選択肢もあり、業務内容やクライアントを自分で選べるのも魅力の一つです。
トラック運転手
トラック運転手は自分のスケジュールに従って業務を行うことが多く、他者からの干渉を受けにくい職種です。
長時間の運転が主な業務であり、職場内の人間関係に悩むことが少ないことから、パワハラやモラハラのリスクが低いとされています。
基本的に一人で行動することが多いため、自分のペースで仕事が進めやすく、ストレスを感じることが少ない環境です。
清掃員
清掃員の仕事は、業務内容がはっきりしており、決まったスケジュールに従って行動するため、コミュニケーションのトラブルが少ない職種です。
個人または少人数での作業が多く、自分のペースを維持しやすい環境にあります。
現場では一人で作業を完遂することも多いので、面倒な人間関係に巻き込まれることが少ないのが特徴です。
そのため、パワハラやモラハラの対象になりにくく、精神的なストレスを感じずに取り組むことができます。
警備員
警備員は職場や建物の安全を守る重要な役割を担っており、独立して業務を遂行することが求められます。
業務内容は事前に定められており、それに従って淡々と対応することが多く、他者との直接的なコミュニケーションが少ないのが特徴です。
これにより、パワハラやモラハラに悩まされることが少ない職場環境が整っています。
警備業務は基本的には一人で行動することが多いため人間関係に気を遣う場面が少なく、自分のペースで仕事ができる点も大きな魅力です。
パワハラやモラハラでの休職に関するよくある質問

最後にパワハラやモラハラでの休職に関するよくある質問を紹介します。
- どれくらいの期間休職できますか?
- 診断書なしでは休職できませんか?
職場のストレスへの対処法を探る手助けになれば幸いです。それぞれ確認していきます。
どれくらいの期間休職できますか?
休職期間は、病状や会社の就業規則、労働契約の内容によって異なります。
通常、産業医や主治医の診断に基づき、1ヶ月から3ヶ月の休職を開始するケースが一般的です。
しかし、回復具合に応じて休職期間が延長されることもあります。
具体的な期間については、会社と相談し医療機関の意見を踏まえて決定するのが望ましいでしょう。
診断書なしでは休職できませんか?
休職には医師の診断書が必要とされることがほとんどです。
診断書は、休職の正当性を証明するだけでなく、給付金の申請や労働契約に基づく手続きにも必要となる場合があります。
そのため、パワハラやモラハラが原因で体調を崩した場合は、早めに医療機関で診断を受け、正式な休職手続きを進めるようにしましょう。
パワハラやモラハラでストレスフルになったら早めにクリニックへ!

パワハラやモラハラは、心の健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、ストレスを溜め込む前に、早めに専門のクリニックで相談することが重要です。
心療内科や精神科では状況に応じた適切なケアを受けることができ、問題の早期解決への一歩となります。
専門家のサポートを受けることで、安心して対処できる環境を整え回復への道を見つけられるでしょう。
なお、パワハラやモラハラでお悩みの方は、よりそいメンタルクリニックにご相談ください。患者様の症状を見極めて適切な治療を提供いたします。