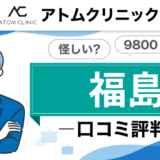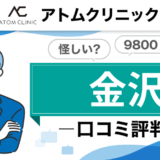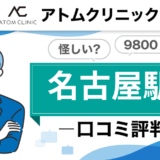「このつらい症状は不安障害?うつ病?」
「病院に行った方がいいのかわからない。治療法はどのようなものがあるの?」
このようなお悩みをお持ちの方は多いでしょう。
不安障害もうつ病もジャンルは同じ精神疾患ですが、主に発症の要因や症状が違います。
この記事では、不安障害とうつ病の違いやそれぞれの診断基準、治療法について紹介します。また、後半に紹介する病気を改善させるコツ3選もおすすめの内容です。
精神的・身体的な症状や悩みを抱えていて、不安障害とうつ病の違いについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
なお、専門医への相談を検討している方は、横浜よりそいメンタルクリニックへご相談ください。経験豊富な専門医が在籍しており、環境面や設備面も充実していて、専門的な治療を受けられます。
不安障害とうつ病の違いとは|主に症状が異なる

不安障害もうつ病も、日常生活に大きく支障をきたしてしまう疾患です。共通している部分もありますが、発症の要因と考えられるものや症状が異なります。
| 不安障害 | うつ病 | |
| 発症の要因と考えられるもの | ・ストレス ・遺伝 ・性格など | ・ストレス ・遺伝 ・性格 ・環境の変化 ・神経伝達物質の減少など |
| 身体的症状 | ・動悸 ・発汗 ・息苦しさ ・震え、めまい ・吐き気など | ・疲れやすい ・倦怠感 ・不眠、過眠 ・食欲の低下、増加など |
| 精神的症状 | ・コントロールできないほどの極度の不安 ・死への恐怖 ・イライラなど | ・落ち込み ・集中力、決断力の低下 ・すべてのことに興味が持てない ・イライラ ・希死念慮、自殺願望など |
不安障害とうつ病は、併発するケースが少なくありません。併発すると悪化しやすいと言われているので、早めの受診がおすすめです。
そもそも不安障害とは?

不安障害とは、度を超えた不安が日常生活に支障をきたすほど長く続いたり頻繁に起き、動悸や息苦しさ、めまい、イライラなどのパニック発作が起きる疾患です。
不安は生きていれば誰しもが感じる感情ですが、いつまでも不安を解消できずに溜め込んでしまうと不安障害のリスクが高まります。
緊張やストレス、不安を感じた日はリラックスや休養を心がけて、なるべく次の日に持ち越さないことが大事です。
うつ病とは?

うつ病とは、一日中気分が落ち込んでいて、何にも興味が持てず楽しめないといった精神症状です。さらに、疲れやすい、不眠や倦怠感などの身体症状で、日常生活に支障をきたします。
うつ病は、脳内神経伝達物質が減少することによって起きると考えられており、薬物療法や精神療法、充分な休養が回復への基本です。
脳内神経伝達物質減少の理由は、継続した身体的・精神的ストレスによるものが一般的です。意欲、やる気がなくなって無気力状態に近づいていきます。
【種類別】不安障害の4つの主な症状

不安障害には、おもに4つの種類があります。
- 社会不安障害(社交不安障害)
- 全般性不安障害
- パニック障害
- 強迫性障害
本項では上記4つの障害をそれぞれ解説します。
社会不安障害(社交不安障害)
社会不安障害とは、人と話すことや人が多くいる場所に強い苦痛を感じる障害です。人前に出ることや外に出ることが怖くなって、社会生活を送れなくなってしまいます。
社会不安障害の方が特に緊張や恐怖を感じやすい場面は、以下の通りです。
- 人前での自己紹介、発表、会議、プレゼンテーション
- 人に見られながらの食事
- 大勢の人がいる場所や空間
- 電話対応
そして上記のような場面の時に起こる社会不安障害のおもな症状は、以下の通りです。
- 動悸、息苦しさ
- 冷や汗
- 頭が真っ白になる
- 赤面
- ほてりやのぼせ
- 手足、声の震え
- 身体の硬直
特に、学校や会社での生活に影響が出てくることでしょう。また、病気とは知らずに「性格のせい」や「甘えているだけ」と思い込んでいて、受診が遅れるケースもあります。
人前に出ることに不安や恐怖を感じていて、苦痛や生きづらさを感じていたら、社会不安障害の可能性がありますので早めの受診をおすすめします。
全般性不安障害
全般性不安障害とは、日常的な活動や出来事に関する不安や心配をいつも漠然と持ち続けてしまう障害です。日常的な活動や出来事とはおもに、仕事・学校・家族・友人・地域社会・健康面・金銭面などです。
長期間にわたり漠然とした不安や心配を感じ、日常生活に支障をきたします。
また、人によっては不安の対象が広く、災害や社会情勢なども最悪のシナリオを考えてしまい、夜眠れなくなったり集中力が低下したりします。
日常生活を送れないほど、漠然とした不安を長期間抱えていたら、全般性不安障害の可能性を疑ってみましょう。
パニック障害
パニック障害とは、予期しない突発的な不安や恐怖が生じて、動悸・めまい・ふるえ・発汗・息苦しさといったパニック発作を繰り返す障害です。パニック発作は通常10分〜1時間程度で治まります。
はっきりとした理由がないのに、突然死んでしまうかと思うようなパニック発作が起きるのが特徴です。
そして、「また発作が起きるんじゃないか」と強い不安を感じるようになり、一人で外に出られなくなるなど日常生活に支障をきたします。
パニック発作は、身体的な異常があって起こるものではないため、身体の治療の必要はありません。発作を抑えるための治療をおこないます。
強迫性障害
強迫性障害とは、不安からある一定の行動や行為を繰り返してしまう障害です。
たとえば、以下が代表的な行動として知られています。
- 手が汚れているのではないかと気になって、一日に何十回も何百回も手を洗う
- 家の鍵を閉めたかが気になって、何度も自宅に戻って施錠の確認をする
強い不安感を持つことを強迫観念、それを打ち消す行為を強迫行為と言い、このふたつが存在して初めて強迫性障害と診断されます。
またこの障害の特徴として、自分の行動が変だという自覚が本人にあることです。
そのため「自分はおかしい」「周囲から変だと思われてしまう」という恐怖から、行動範囲がせまくなってしまうことがあります。
【チェックリストあり】不安障害やうつ病を自分でチェックする方法

「病院に行く前に、まずは自分で簡単にチェックしてみたい」方にむけて、この項では下記2つを紹介します。
- 不安障害の診断基準(DSM-5)
- うつ病の診断基準(DSM-5)
現在では、おもに「DSM-5」と「ICD-10」の2つの基準があります。DSM‐5はAPA(米国精神医学会)が定めたものです。これに対して ICD-10はWHO(世界保健機関)による基準です。
ここでは、DSM-5を紹介します。なお、このチェックリストはあくまでも参考程度にして、正確な診断は医師にご相談ください。
不安障害の診断基準(DSM-5)
不安障害の診断基準(DSM-5)は以下の通りです。
| 不安障害(DSM-5)内容 | チェック | |
| A | 他者の注目を浴びる可能性のある1つ以上の社交場面に対する、著しい恐怖または不安があること (社交場面の例:雑談、知らない人と会う、誰かと食べたり飲んだりする、談話をするなど) | 🔲 |
| B | 自分の取る行動や不安な態度が変に思われるのを恐れる (恥をかいたり、拒絶されることなど) | 🔲 |
| C | その社会的場面はほとんど常に恐怖や不安を引き起こす | 🔲 |
| D | その社会生活場面を回避する、あるいは強い恐怖や不安を持ちながらひたすら我慢する | 🔲 |
| E | 恐怖や不安は、その社会生活場面が持つ実際の脅威やその社会の文化的背景に釣り合わない | 🔲 |
| F | 恐怖や不安、回避は持続的であり、一般的には6ヵ月以上続く | 🔲 |
| G | 恐怖や不安、回避は、臨床的に大きな苦痛、または社会的・職業的、他の重要な機能の障害をもたらしている | 🔲 |
| H | 物質(依存性薬物・医薬品)または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない | 🔲 |
| I | パニック障害・醜形恐怖症・自閉症スペクトラム障害などではない | 🔲 |
| J | 他の疾患がある場合でも、恐怖、不安、回避はそれとは関係せず、その症状が顕著である | 🔲 |
うつ病の診断基準(DSM-5)
| うつ病(DSM-5)内容 | チェック | |
| 1 | ほとんど毎日、一日中ずっと気分が落ち込んでいる | 🔲 |
| 2 | ほとんど毎日、一日中ずっと何に対する興味もなく、喜びを感じない | 🔲 |
| 3 | ほとんど毎日、食欲が低下(増加)し、体重の減少(増加)が著しい | 🔲 |
| 4 | ほとんど毎日、眠れないもしくは寝過ぎている | 🔲 |
| 5 | ほとんど毎日、話し方や動作が鈍くなったり、イライラしたり、落ち着きがなくなったりする | 🔲 |
| 6 | ほとんど毎日、疲れやすかったり、やる気が出なかったりする | 🔲 |
| 7 | ほとんど毎日、自分に価値がないと感じたり、自分を責めるような気持ちになる | 🔲 |
| 8 | ほとんど毎日、考えがまとまらず集中力が低下して、決断できない | 🔲 |
| 9 | 自分を傷つけたり、死ぬことを考えたり、その計画をたてる | 🔲 |
複数の項目に当てはまる場合は不安障害やうつ病の可能性があります。早めに医療機関に訪れて診断を受けましょう。
不安障害やうつ病を治療する3つの方法

不安障害、うつ病ともに治療の基本は以下の3つになります。
- 精神療法
- 薬物療法
- 充分な休養
それぞれ解説します。
精神療法
精神療法(心理療法)とは、心理学的な理論などに基づいておこなわれるアプローチによって考え方や行動、人間関係などを少しずつ変えていく方法です。
おもにカウンセリングなどの対話を通じて、問題や悩みをきちんと理解し、解決していくことが目標になります。
特に不安障害やうつ病の精神療法としてよくおこなわれているのが、認知行動療法です。
現実の受け取り方や、ものの見方のことを「認知」といい、その認知の歪みを直していくことで気持ちを楽にしていきます。
薬物療法
不安障害やうつ病には、一般的に抗うつ薬や抗不安薬が使われます。
抗うつ薬は、おもにSSRI(選択的セロトニン再阻害薬)が使われ、脳内の神経伝達物質を調整してくれます。効果が出るまでに、少し時間がかかるのが特徴です。
抗不安薬では、ベンゾジアゼピン系抗不安薬がおもに使われます。使い続けると効果が薄れてしまう可能性があることが特徴です。
種類が多いので、専門医の判断を聞いて自分に合った適切な薬を服用してください。
自分の判断で勝手に服用をやめてしまうと、思わぬ副作用が出ることもあるので気をつけましょう。
充分な休養
不安障害やうつ病は、ストレスを溜めないようにゆっくり休むことが重要です。
学校や会社、家事などの環境を今一度見直して、過剰なストレスや疲労が溜まらないように調整してみましょう。そのためには、周りのサポートも必要です。
家族や会社の同僚、友人などに相談しながら、ときには頼ったり、無理なことは断ったりしてみましょう。無理のない環境を整えて、休養に集中することがとても重要です。
不安障害やうつ病を回復に向かわせるためのコツ3選!

不安障害やうつ病は、自分で行動することで回復に近づきます。特に大事なポイントは以下3つです。
- 病気を理解して、自分自身を知る
- 身体の緊張をほぐして心からリラックスする
- 生活リズムを整える
それぞれのポイントを確認していきましょう。
病気を理解して自分自身を知る
不安障害やうつ病のほかにも、精神疾患はあります。複数の病気が併発していることもあるでしょう。まずは、自分の病気を知るところから治療はスタートします。
治療していくうえで、周りのサポートも大切ですが、自分自身も正しい知識をつけることで、一歩一歩回復に進んでいきます。
元気が出ない時は、横になっても大丈夫です。少し余裕があるときに、本で病気について学んでみるといいかもしれません。
精神疾患にも症状には個人差があります。不安障害であれば、「自分は特にこういう場面や状況で不安になりやすい」であったり、うつ病だと「これをしたら少し調子が良くなった」などがあると思います。そういった情報をメモすることも大事です。
そうして自分の特性が分かってくると対処方法が立てやすくなり、つらさが軽くなっていくことでしょう。
身体の緊張をほぐして心からリラックスする
身体は休んでいても、ネガティブな考えごとをしていたりすると精神的に、完全には休まりません。心からリラックスすることを意識してみましょう。
不安障害やうつ病の症状があると、うまくいかずに焦ることもあるかと思います。ですが焦りはよくありません。治そうと努力する気持ちは素晴らしいことですが、自分のペースが大切なのです。
また、周りと比較して落ち込むこともあるかもしれません。しかし今は周りのことはあまり気にせず、つらい時は無理せずに過ごしましょう。とにかく休むことを最優先にしてください。
なお、激しいものでなければ、好きなことを少しやってみるのもおすすめです。落ち着ける趣味で、気分転換してみましょう。
- お風呂にゆっくりと浸かる
- マッサージやストレッチをする
- 散歩する
生活リズムを整える
規則正しく、一日の生活リズムを安定させることは、不安障害やうつ病の症状を軽くするための大事な要素のひとつです。
症状が重度の方も、なるべく生活習慣を乱さないように心がけましょう。心がける内容としては、以下の行動が挙げられます。
- 決まった時間に起床して、決まった時間に就寝する
- 外に出て日光を浴びる
- 1日3食バランスよく栄養を取る
- 軽く運動してみる
- スマートフォンを見すぎない
特に適度な運動や、外にでて日光を浴びることは、神経伝達物質であるセロトニンの分泌を促してくれます。不安障害やうつ病は、セロトニンの減少が原因の一つと言われているので、効果が期待できます。
生活にメリハリをつけ、自律神経も整えることで、不安障害やうつ病の回復スピードも早まることでしょう。
症状がつらい人は早めの受診を

不安障害とうつ病は、おもに症状と発症の要因が異なります。
どちらも生活に支障をきたすつらい症状が起こるため、我慢せずに早めの受診をおこないましょう。患者さんの症状に合った治療法があり、専門医が提案してくれます。
横浜よりそいメンタルクリニックでは、不安障害やうつ病にも専門的に対応が可能です。
土日診療可で、待合室も広く、通院の負担が少ないクリニックとなっております。患者さんの悩みにも寄り添いますのでまずはお気軽にご相談ください。